勤務医時代。私が担当した心臓病のお子さんの中には、治療の甲斐も無く亡くなっていく方が何人もいました。
その死に対して、残念に思うだけでなく、間接的あるいは直接的にも責任を感じることが多々ありました。
先天性心臓病の赤ちゃんは、生まれたときから、あるいは生まれる前から、ご家族の人生を変えてしまいます。
最初は混乱し、悲嘆に暮れ、しかし病気を受け入れ、わが子に愛情を注ぐ親御さんの姿がそこにはあります。
子どもと共に親御さんも成長して強くなっていく様子を見ながら、私は畏敬の念を抱いて診療にあたりました。
新生児期から乳幼児期にかけて、何度も何度も心臓手術を繰り返さなければならないお子さんがいます。
1回の手術で完治する子がいる一方で、1歳の誕生日を迎えられないお子さんもいます。
家族の愛情に包まれて何年も頑張ってきた命が、ついに幼児期や学童期に失われるのはとくに辛いことです。
「よく頑張ったね」という言葉を、臨終のときに私はとても軽々しく口にはできませんでした。
昨日のTBS日曜劇場『19番目のカルテ』(第2話)では、そのような心臓病の少年の死が描かれていました。
少年の兄の口から「ホッとした」という言葉が出ましたが、それを安易に吐かせてほしくはなかったですね。
彼の罪悪感を表現したかったのでしょうけど、死の直後からホッとする家族などいないと、私は思っています。
その思いに至るまでの苦悩から、弟の病状急変に関わる出来事までを、もっと丁寧に見せてほしかった。
ドラマでは、闘病中の子どもを置いて母親が家を出て行った設定でしたが、それも私には違和感があります。
父親が離れていった事例なら、実は残念ながら数多く見てきましたが、母親のケースは見たことがありません。
夫婦の関係がどうであれ、病気を持って生まれてきたわが子と母親の絆は、簡単に切れるものではないはず。
深みのあるストーリーに仕立てようという趣旨は理解しますが、大事なところの描写不足が残念なドラマです。
(写真はTBSのサイトより)



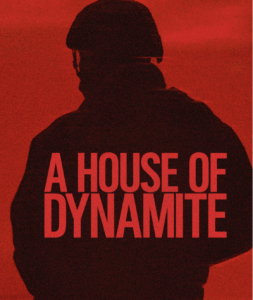
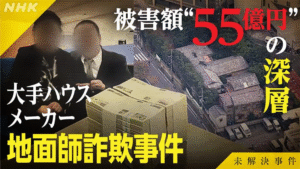



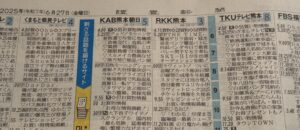

コメント