「百日咳」流行のニュースを見たり聞いたりするたびに、その表記と発音が気になります。
テロップに「百日せき」と表示され、キャスターが「ヒャクニチセキ」と言うからです。違和感があります。
医療従事者が日頃使うのは、「百日咳」であり「ヒャクニチゼキ」です。「ゼキ」です。濁ります。
小児科学会が予防接種啓蒙ポスターを作ってますが、そこにも「ひゃくにちぜき」と明確に記載されています。
「セキ」が「ゼキ」に変化するのは、複合語の「連濁」という、ごく自然な現象です。
「本棚」とか「長靴」とか、「回転寿司」とか「あとぜき」のような感じです。
連濁に限らず言葉の読み方は、それが楽に発音できる方向に変化しがちです。
手元の辞書で百日咳を引くと、日国「ゼキ」、大辞泉「ゼキ」、新明解は第8版から3版まで全部「ゼキ」。
あろうことか、「NHK日本語発音アクセント新辞典」でも「ゼキ」ですよ。調べた限りオール「ゼキ」。
ところがですよ。厚労省のサイトには「百日せき」と記載されているのです。これが元凶なんですかね。
メディアもこれに従ってるのでしょうけど、私には「回転すし」と同様の違和感があるし、発音しにくいです。
一方で、国立健康危機管理研究機構(旧感染研)のサイトには「百日咳」とあり、厚労省とは異なります。
ただし、読み方の記載はなく漢字だけが使われていて、あえて読みには触れようとしない印象すらあります。
連濁にかぎらず、メディアと医療界の間には、医療・医学用語の読み方でしばしば乖離があります。
たとえば「腹腔鏡」。メディアでは「フククウキョウ」、医療現場では「フックウキョウ」と「促音便」です。
常に業界優先の読み方にしろとは言いませんが、患者さんが病院でよく耳にする読み方に向かうべきでしょう。
目次
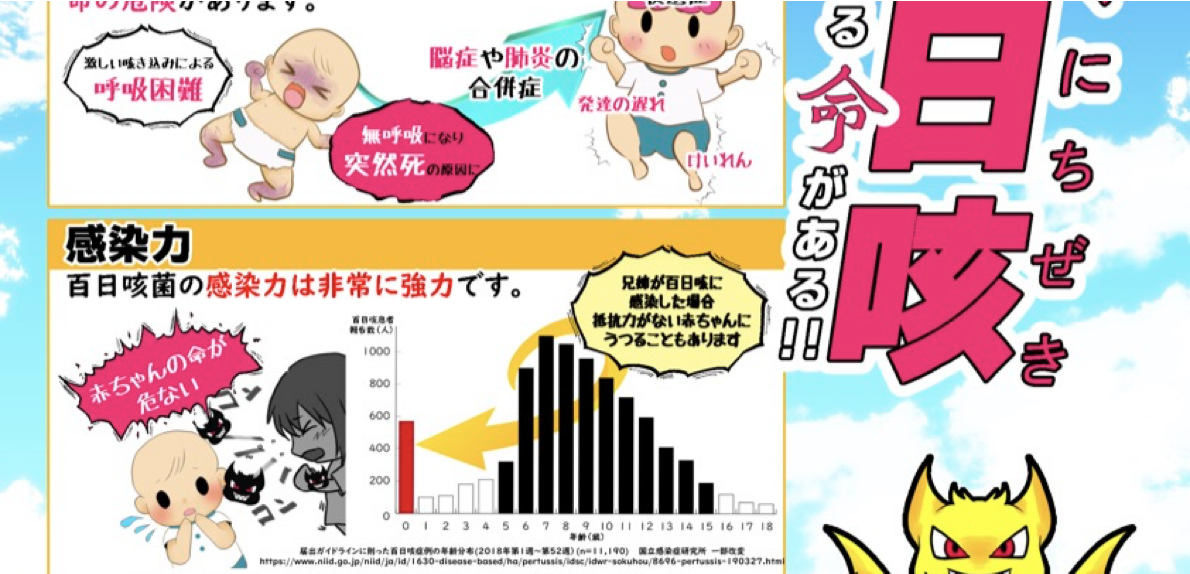
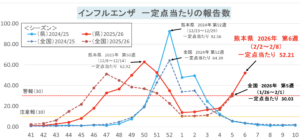
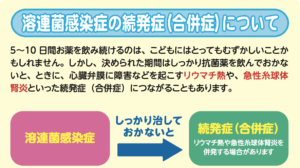
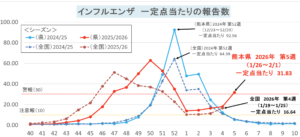

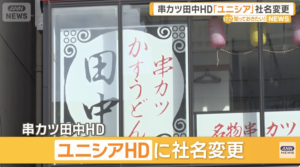
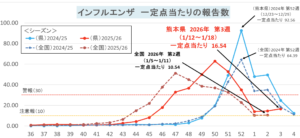

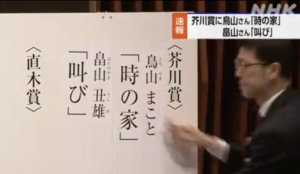
コメント